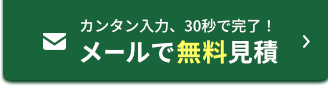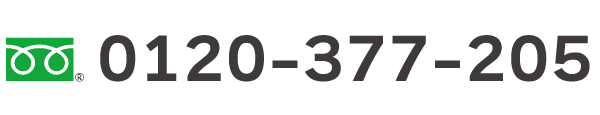初詣や七五三、成人式など、特別な行事で着る機会が多い日本の伝統衣装「着物」。
しかし、そんな大切な思い出が詰まった着物も「とっておきたいけど保管場所に困る」「カビや虫食い対策が大変」など、日常の管理で悩む方も少なくありません。
着物は頻繁に着るものでもないため、長くたんすの中に眠ったままになっていることも多いでしょう。もしお困りなら、思い切って処分を検討してみるのもひとつの方法です。
そこでこの記事では着物の捨て方を詳しく紹介します。
ただ捨てるだけでなく、リサイクルや思い出を残す方法、買取価格のコツも解説しますので、ぜひ参考にしてください!
▼この記事でわかること
- 着物の処分方法
- 着物を高く買い取ってもらうコツ
- 着物を処分する際の注意点
着物の処分方法は8通り!

着物の処分方法は以下の8通りです。
- 可燃ごみや資源ごみとして処分する
- 自治体の古着回収ボックスを利用する
- 着物買取専門店に買い取ってもらう
- フリマアプリ・オークションへ出品する
- 寄付する
- 友人・知人に譲る
- リメイクする
- 不用品回収業者に依頼する
それぞれのメリットや注意点を理解し、自分に合った方法で着物を手放しましょう。
可燃ごみや資源ごみとして処分する
着物を手軽に処分したいのなら、自治体の可燃ごみや資源ごみとして出す方法があります。自治体のごみ収集なら、特別な費用はかからず、ごみ袋代のみで処分できるのがメリットです。
ごみの分別ルールについては、以下のように各自治体で異なります。
| 地域 | ごみ区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市 | 資源ごみ (着物・着物の帯) | 集団資源回収・リサイクルステーションが 利用できない場合は、 「可燃ごみ」として出す |
| 愛知県岡崎市 | 古着回収 | ひどい汚れ・破れがなく、濡れていないもの |
| 静岡県静岡市 | 可燃ごみ | 自治会・町内会で古布回収を 行っている場合はそちらを優先する |
| 東京都多摩市 | 古布 | ・清潔でそのまま着られる状態のものに限る ・汚れているものは「燃やせるごみ」として出す |
| 埼玉県志木市 | 布類 | 着用できないものは、50cm×50cm切って「可燃ごみ」として出す |
着物は古着や古布としてリサイクルに回せますが、状態によっては可燃ごみとして出す必要があります。
手軽に処分できる一方で、思い入れのある着物をごみとして捨てるのに抵抗がある方もいるかもしれません。その場合は、リサイクルやリメイク・寄付などを検討してみてください。
古着回収ボックスを利用する
着物を無料で処分したい場合、古着回収ボックスを利用するのもひとつの方法です。
古着回収ボックスは、スーパーの駐車場や公共施設の敷地内など、日常生活のなかで立ち寄りやすい場所に設置されています。回収された衣類は、綿の原料やウエスとして再利用されるため、燃えるごみとして処分するよりも環境に配慮した方法です。
たとえば、東京都大田区では地域に6か所の回収ボックスが設置されており、着物や帯を袋に入れて投入することが可能です。
一方、愛知県名古屋市では衣類・布類を資源として回収しており、回収ボックス「PASSTO」に投入できますが、着物は回収対象外となっています。
各地域によって回収対象の品目や設置場所が異なり、施設の営業時間内に持ち込まないと利用できないため、事前に確認することをおすすめします。
着物買取専門店に買い取ってもらう
着物をお得に手放すなら、着物買取専門店を利用するのがおすすめです。アンティークやブランド着物・高級素材で作られた着物は、高額で買取してもらえる可能性もあります。専門知識を持ったスタッフが丁寧に査定し、適正な価値を見極めてくれるのが特徴です。
一方、一般的なリサイクルショップでも着物の買取を依頼できますが、注意が必要です。多くの場合、洋服と同じ基準で査定されるため、高価な着物でも低い価格になるリスクがあります。
着物買取専門店は、留袖・振袖・訪問着・小紋など、幅広い種類の着物を取り扱い、丁寧なお手入れや寸法直しを経て再販売する仕組みを持っています。
店舗に持ち込む時間がない方は、郵送買取や出張買取を利用するのが便利です。
また、オンラインで査定を依頼すれば、事前に買取価格の相場を把握できるので安心です。信頼できる着物買取専門店を選び、大切な着物を適切にリユースしましょう。
着物以外の買取可能な骨董品については、こちらの記事でも詳しく解説しております!
フリマアプリ・オークションへ出品する
まだ着られる着物を売却するなら、フリマアプリやオークションサイトに出品する方法もあります。メルカリやヤフーオークションなどのオンラインプラットフォームなら、簡単に登録・出品ができるので初心者でも利用しやすいのが魅力です。
直接、着物を欲しがっている人とつながれるので、店舗で買取を断られたものでも売れる可能性があります。
また、自分で価格を設定できるため、納得のいく金額で着物を手放せる点も大きなメリットです。
メルカリでは、以下のような中古着物が取引されています。
- 正絹 付け下げ:11,700円
- 七五三 子供着物:4,790円
- 羽織 6点セット:3,900円
トールサイズの着物やリメイク用の反物も売れている印象です。
出品の際は、複数枚の着物の写真や、寸法・汚れの有無などの説明を記載して商品の状態を正確に伝えることがポイントです。
注意点として、販売価格を低く設定しすぎると、送料や手数料を差し引いたときに赤字になる可能性があります。需要があれば古いものも売れる可能性があるので、処分を急いでいない場合は出品してみると良いでしょう。
寄付する
リサイクルショップやオンラインプラットフォームで着物が売れない場合、NPO法人といった団体に寄付する方法もあります。
単に捨てるのではなく、新たな場所で役立ててもらえるため、思い出の詰まった着物も気持ちよく手放せることがメリットです。
ただし、NPO法人へ着物を寄付する際は、送料や手数料がかかる場合があります。負担に感じる場合は、別の方法も検討しましょう。
当社「ユースマイル」では、着物は受け付けておりませんが、子供服やタオルなどの不用品をお預かりしております。寄付いただいた品物は、発展途上国での雇用創出やワクチン支援に役立てられます。
ご興味のある方は、ぜひ以下のリンクから詳細をご覧ください!

友人・知人に譲る
着物が好きな友人や知人が身近にいるのなら、直接譲るのもおすすめです。着物はサイズの幅が広いため、体型が合わなくても少し手直しすれば着られます。
そのため、自分にとって不要になった着物でも、他の誰かにとっては喜ばれる贈り物になる可能性があるのです。
着物を普段から着る人や、着付け教室に通っている人がいれば、いらなくなった着物を引き取る意向があるか聞いてみましょう。
近くに譲る相手がいない場合は、SNSや地域の掲示板「ジモティー」を利用して着物がほしい人を見つける方法もあります。
大切に使ってくれる人に渡せれば、着物が無駄にならず、安心して手放せるでしょう。
リメイクをする
思い入れのある着物や、美しい柄や素材を捨てるのが惜しいと感じる場合は、リメイクするのも良い方法です。
特に、汚れやシミが原因で売れない着物でも、布の一部を再利用することで、再び活躍させられます。
- バッグ
- ポーチ
- クッションカバー
- ベスト
- ワンピース
裁縫が得意な方なら、これらを手作りして楽しむのも良いでしょう。
また、絹や麻などの高級素材で作られた着物であれば、一部を切り取って額に入れ、絵画のように壁に飾るのも素敵ですね。裁縫が苦手な方でも無理なくできるため、壁を飾るだけでなく、思い出の着物を記念に残したい場合にも大変おすすめです。
不用品回収業者に依頼する
早急に古い着物を処分したいのなら、不用品回収業者に依頼するのもひとつの手段です。不用品回収業者なら、自宅まで引き取りに来てくれるため、着物を手間なく捨てられます。
不用品回収業者に依頼するメリットは以下の通りです。
- 電話1本で依頼できる
- 土日や夜間も対応可能
- ほかの不用品も同時に回収
- 着物や帯・小物の買取査定もOK
- 大量の着物も自宅から搬出してくれる
ただし、不用品回収は有料になるため、着物1点だけなら、自治体の回収サービスに出すほうが安く済むでしょう。
そのため、着物以外に捨てたい家電や大型家具があるのなら、まとめて不用品回収業者に依頼するのがおすすめです。たとえば、着物を保管していた和ダンスも不要になるなら、一緒に回収してもらうと効率的です。
着物以外の回収可能な骨董品については、こちらの記事もご覧ください!
費用やサービス内容は業者によって異なるため、まずは2~3社に無料見積もりを取って比較検討してくださいね。
安心して依頼できるおすすめの不用品回収業者についてはこちらの記事で詳しく解説しております!
着物を捨てる際にかかる費用相場

着物を捨てる際にかかる費用は、処分方法により異なります。
| 処分方法 | 費用 |
|---|---|
| 可燃ごみ・資源ごみ | 指定ごみ袋代 |
| 古着回収ボックス | 無料 |
| 着物買取専門店 | 無料(買取による収益あり) |
| フリマアプリ・オークション | 無料(売買による収益あり) |
| 寄付する | 送料・手数料 |
| 友人・知人に譲る | 無料 |
| リメイク | 無料 |
| 不用品回収業者 | 1点:5,000円~ トラック積み放題プラン:33,000円~ |
基本的に着物の処分は無料でできる場合が多いです。状態の良い着物なら、売却することで現金化できる可能性もあります。
時間をかけられない方や大量の不用品でお困りなら、不用品回収業者に依頼する方法を検討しましょう。業者によっては、トラックの荷台に積める分を一律料金で回収してもらえる「積み放題プラン」が利用でき、効率よく処分できます。
また、買取できる不用品が多いと、その金額分が費用から差し引かれるため、結果的にお得になることも。着物の種類や状態、捨てる際の優先事項などを考慮して、自分に合った処分方法を選んでくださいね。
着物を高く買い取ってもらう5つのコツ

着物を高く売るためには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 希少性のある着物を売る
- 保存状態をきれいに保つ
- 証紙を用意する
- 需要のある時期に売る
- 複数の買取業者で査定してもらう
少しでも高値で売却したい方は、ぜひ参考にしてください。
希少性のある着物を売る
希少性のある着物は、高額で買取される傾向にあります。
たとえば、有名な作家や職人が作ったもの・伝統工芸品・特定のデザイナーが手掛けた着物などが該当します。
- 染物作家:友禅染・紅型(びんがた)・江戸小紋
- 織物作家:結城紬・芭蕉布・羅(ら)・大島紬
- デザイナー:ツモリチサト・コシノジュンコ・桂由美など
これらの着物を高値で売るには、適切に査定できる業者に依頼することが重要です。査定士は、着物の状態やブランドなどから正確な価値を判断するための専門知識を持っています。
ただし、すべての買取業者が着物の査定に詳しいわけではありません。公式サイトや問い合わせで業者の信頼性を確認し、専門性の高い業者を選ぶことをおすすめします。
保存状態をきれいに保つ
どんな着物でも、保存状態が良いものは高値がつきやすいです。
- 汚れやシミがない
- 虫食いやカビがない
- ニオイやシワがない
保存には湿気を防ぐ「桐たんす」を利用するのが理想的です。
また、湿気の多い時期には「外干し」を行い、カビを防ぎましょう。長期間保管する場合でも、定期的に状態を確認してメンテナンスすることで、価値を保てます。
証紙を用意する
証紙は着物の品質や産地を証明する重要なものです。証紙があると査定士が価値を正確に判断できるため、査定額が大きく上がる可能性があります。
また、箱や付属品が揃っていればさらに高額で取引されることがあります。
参考:京都友禅協同組合|証紙
需要のある時期に売る
着物の買取価格は、シーズンによって大きく相場が異なります。
成人式や卒業式、入学式などのイベントが多い1月から4月は、着物の需要が最も高まる時期です。
なかでも振袖や喪服、訪問着といった着物に人気が集中するので、たんすに眠っている着物があるのなら、買取に出すことをおすすめします。
ただし、ピークが過ぎると需要は一時的に減少するため、買取価格も下がる傾向があります。
そのため、すぐに売却する必要がない場合は、需要が高いタイミングを見計らって査定に出すと良いでしょう。
複数の買取業者で査定してもらう
着物を高く売るためには、複数の買取業者に査定してもらうことが大切です。
業者ごとに査定基準や市場の需給状況が異なるため、同じ着物でも査定額が大きく変わることがあります。
そのため、少なくとも3社以上の査定を受けるのがおすすめです。
近くに着物を買い取れる業者がない場合は、着物を郵送して査定してもらえるサービスもあります。買取サービスの中には手数料や送料がかかる場合があるため、事前に費用を確認してから利用しましょう。
ただし、買取不可の場合でも費用が発生することがあるため、希少性が高い着物に限定して依頼するのがおすすめです。査定価格に自信がない場合は、ほかの処分方法も検討してください。
着物を処分する際の注意点

ここでは着物を手放す際の注意点を解説します。
古くて状態の悪い着物は買取が難しい
売れない着物にはいくつかの特徴があり、以下に該当する場合は買取を断られることが多く、処分方法が限られてしまいます。
| 買取が難しい着物 | 特徴 |
|---|---|
| 汚れや傷みが目立つ | シミやカビ・刺繍の剥がれなどがある |
| 臭いがきつい | 湿気やカビ・タバコ・ペットの臭いが付いている |
| 素材が絹以外 | ウールや化学繊維などの着物 |
| 定形外のサイズ | 小さすぎる、または特別に大きいサイズの着物 |
これらの当てはまる場合は、フリマアプリやオークションに出品するか、処分するのが賢明です。
後悔なく捨てる基準を決める
着物を処分する際、後悔しないためには基準を明確にすることが重要です。
まず「どんな着物を残し、どれを手放すか」という基準を考えてみましょう。
たとえば、「この1年で一度も袖を通さなかった」「未来の自分が着るイメージが湧かない」と感じる着物は、思い切って処分するのがおすすめです。
逆に、「見るだけで嬉しくなる」「特別な思い出がある」といった着物は、リメイクして形を変えたり、大切に保管したりする方法もあります。
悪質な押し買い業者に注意する
着物を処分する際、訪問買取を装った悪質な業者に注意が必要です。「不用品を何でも引き取る」と電話で勧誘されても、実際には貴金属をしつこく要求するケースが報告されています。こうした業者は、強引に高額請求することがあり、不安を感じる方も多いです。
安全に対応するためには、以下の点を守りましょう。
- 訪問業者に古物商許可証の提示を求める
- 不用品回収を依頼する際は事前に見積書を提示してもらう
- 不審な場合は消費生活センターや警察に相談する
依頼していないのに突然訪問してくる業者には特に注意が必要です。冷静に対応し、トラブルを防ぎましょう。
着物を処分する際に出やすい不用品

着物のような、自宅の片付けで出てくる不用品の処分方法については、こちらの記事もご覧ください!
着物の処分でよくある質問

Q.着物一点だけでも回収してもらえますか?
A.少量の不用品向けのプランがございますので、一点のみのご依頼でも問題ございません。
もちろん、着物以外の不用品回収のご希望がございましたら、その場でまとめて無料でお見積もりいたします。
Q.休みが不規則なのですが、前日や当日に依頼できますか?
A.はい、当社は年中無休で営業しております。
ご連絡をいただければ、地域内を巡回しているトラックの中で近くのスタッフが向かいますので、最短30分程度でお伺いいたします。お客様のご都合がつきましたら、ご連絡をお待ちしております。
Q.きれいな状態の着物なら買い取ってもらえますか?
A.当社には買取対応の部門もございますので、お客様が大切に保管なさってきた着物をできるだけ再利用できるように査定いたします。
買取が可能な場合には、処分費用から買取代金を差し引きます。
Q.見積もり後のキャンセルは可能ですか?また、電話やメールでの見積もりはできますか?
A.もちろん可能です。その場合でも出張や見積もりの料金はご請求いたしませんので、安心してお問い合わせください。
着物一点などの少量の場合でしたら、お電話やメールで概算の見積もりをご依頼いただくことも可能です。
Q.着物の帯だけでも回収することは可能ですか?
A.はい。可能です。
どんなものでも、どんな数でも回収することができます。見積もりの際にお申し出ください。
Q.着物と一緒に大きな家具は回収してもらえますか?
A.はい。可能です。家具のほかにも、家電や割れたガラス、土など様々な品目を回収しております。
また、お得なパックプランもございます。ぜひお気軽にご相談ください。
着物の処分は出張回収センターにおまかせください!

着物の処分方法は主に以下の通りです。
- 可燃ごみや資源ごみとして処分する
- 自治体の古着回収ボックスを利用する
- 着物買取専門店に買い取ってもらう
- フリマアプリ・オークションへ出品する
- 寄付する
- 友人・知人に譲る
- リメイクする
- 不用品回収業者に依頼する
着物を処分したいのなら、ブランドや生地の素材、状態をチェックして捨て方を検討しましょう。
処分方法には、ごみとして捨てるだけでなく、リサイクルや買取もあります。
希少性のある着物や証紙が付いているもの、保管状態が良好な着物なら、買い取ってもらえる可能性が高いです。
また、着物以外の不用品も処分したい場合は、不用品回収業者に依頼するのもおすすめです。
愛知県名古屋市の出張回収センターでは、着物をはじめとする不用品の回収・買取を承っております。最短で即日対応できるため、早く片付けを終わらせたい方は、お気軽にお問い合わせください!
ーこちらの記事もおすすめですー