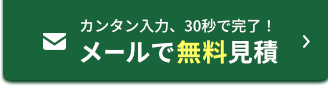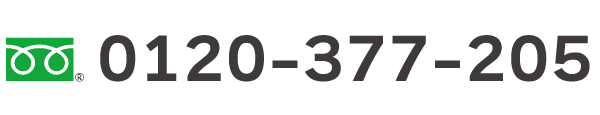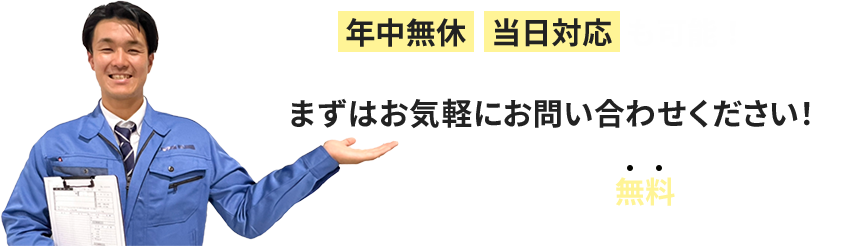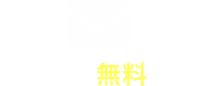今も昔もとても人気のある娯楽・趣味である「釣り」。
釣り好きの方にとっては道具を揃えることも楽しみのひとつですが、意外と知らないのが釣竿の処分方法です。
釣竿にはさまざまな大きさ、材質があるため、どの捨て方が最適かわからない方もきっと多いのではないでしょうか。
高価な釣竿であれば、尚更ごみとして捨てるのは気が引けますよね。
そこで今回は、釣竿の詳しい処分方法や、お得な売却方法について紹介します。
いらなくなった釣竿の処分を検討される方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼こちらの記事でわかること
- 釣竿の処分方法
- 釣竿を処分する際の注意点
釣竿の処分方法は全部で7通り!

釣竿の処分方法は以下の7つです。
- 分解し不燃ごみ・可燃ごみとして処分する
- 粗大ごみとして処分する
- リサイクルショップや専門店で売却する
- フリマアプリやネットオークションに出品する
- 人に譲る・ジモティーを利用する
- 支援団体へ寄付する
- 不用品回収業者へ依頼する
それぞれの処分方法について詳しく見ていきましょう。
①分解し不燃ごみ・可燃ごみとして処分する
釣竿は指定のごみ袋に入る大きさまで分解できれば「不燃ごみ」「可燃ごみ」といった普通ごみとして処分可能です。
不燃・可燃ごみの場合は自治体の指定ごみ袋に入れ、回収日に捨てるだけで手軽に処分できるでしょう。
まずは竿とリールに分解し、釣り針やおもり、釣り糸といった部品を外す必要があり、それぞれのパーツがどの分別方法になるのか、自治体のルールを確認した上で処分するようにしてください。
一般的に釣竿は以下のように分別されます。
| パーツ | 分別区分 |
|---|---|
| 釣竿(一辺の長さが30cm以下・50cm以下など) | 可燃ごみ・不燃ごみ |
| 釣竿(一辺の長さが30cm以上・50cm以上など) | 粗大ごみ |
| リール | 不燃ごみ |
| 釣り針・金属製のおもり | 不燃ごみ |
| 釣り糸 | 可燃ごみ |
釣竿の素材はカーボンが主流ですが、ほかにも竹やガラス繊維から作られたグラスや、ホウ素繊維を使用したボロンなどが挙げられます。
どの素材が使用されているかによって、分別区分が変わる自治体もあれば「釣竿」と一括りに分別区分が決まっていることも。
大きな釣竿であれば「粗大ごみ」となることが多いですが、小型の場合は自治体によって分別が異なりますので、前もって確認しておきましょう。
②粗大ごみとして処分する
お持ちの釣竿が「粗大ごみ」と分別される場合、予約が必要になることがほとんどです。
多くの自治体ではインターネットや電話などで申し込みし、指定された日時に釣竿を収集場所へ出しておきます。粗大ごみの回収日は月に1回程度のところが多いため、時間に余裕を持って申し込みしましょう。
一般的な自治体での粗大ごみの利用手順は以下のとおりです。
- 自治体のホームページや電話から申し込みをする
- 手数料納付券(シール)をスーパーやコンビニなどの指定販売店で購入する
- シールに受付番号や氏名などの必要事項を記入し、釣竿に貼る
- 指定された日時に指定場所へ出す
例として、以下の自治体での釣竿の分別区分と粗大ごみの手数料を紹介します。
| 地域 | 釣竿の分別区分 | 粗大ごみ手数料 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市 | 粗大ごみ | 10本までを1組として250円 |
| 静岡県浜松市 | 燃えるごみ(60cm未満) 連絡ごみ(60cm以上) | 5本までごとに310円 |
| 神奈川県横浜市 | 燃やすごみ(50cm未満) 粗大ごみ(50cm以上) | 15本までを1組として200円 |
見ていただくとわかるとおり、釣竿は数本まとめて捨てても費用が同じになることが多いようです。
なお、釣竿を出す際、先が折れていたり尖ったりしている場合は、回収作業員がケガしないよう紙で包んで排出するようにしましょう。
ごみ処理施設へ持ち込むことも可能
できるだけ早く釣竿を処分したい場合、ご自身で自治体のごみ処理施設へ持ち込んで処分する方法もあります。
ごみ処理施設では重さによって処分料金が決まることがほとんどなため、通常の粗大ごみ収集に出すよりもさらに安く済む可能性が高いです。
以下はごみ処理施設への自己搬入について記載のあった自治体の一例です。
ただし、車への積み下ろしや運搬は自力で行わなくてはいけません。
また、基本的に車での搬入しか利用できないため、移動手段がない場合には不向きな方法と言えるでしょう。
③リサイクルショップや専門店で売却する
状態がいい釣竿をお持ちなら、リサイクルショップや釣具専門店へ査定に出してみましょう。
買い取ってもらえれば処分費用が浮く上に臨時収入にもなり、新しい釣竿の購入資金にもなりお得です。
釣竿を含め、釣具はさまざまなメーカーから販売されていますが、中でも人気なのは以下のメーカーです。
- ダイワ
- シマノ
- ジャッカル
- アブガルシア
- ティムコ
- メジャークラフト
- がまかつ
- 東レ
- グローブライド
- スミス
- G-クラフト
- ピュアフィッシング
- ダイコー
- ウエダ
- プロックス
これらの人気メーカーの釣竿は中古需要も非常に高いため、高額査定も期待できます。
釣竿の買取は同じメーカーのものであってもモデルによって大きく異なるため、同じメーカー、モデルの買取実績を確認しておきましょう。
ただし、リサイクルショップの多くは専門的知識のない場合が多いです。
その点、釣具専門店であれば、釣具全般の知識を持つスタッフが多く在籍しており、再販ルートを持っていることが多いため、高値で買い取ってもらえる可能性がグッと上がります。
釣竿の購入額が高かった場合や、人気モデルの場合は思ってもみない額で買い取ってもらえる…なんてことも。
なお、専門店であっても店舗ごとに取り扱いできる製品に違いがありますので、事前に確認を済ませておきましょう。
④フリマサイトやネットオークションに出品する
釣竿を売却したいなら、フリマサイトやネットオークションを利用するという手もあります。
こうしたサイトを利用する大きなメリットは「自分で売り価格を決められる」という点でしょう。
買取店とは違い、自分で価格を決められることで納得いく金額で売ることが可能になります。
ただし、フリマアプリやネットオークションは気軽に釣竿を処分できて便利な手段ではあるのですが、その反面、下記のようなデメリットもあるため注意が必要です。
- 出品から梱包、発送まですべて自分でするため手間がかかる
- 売れた場合は配送料と手数料がかかる
- 説明していたより釣竿の状態が悪いとクレームになることも
やみくもに高い金額を付けると売れなかったり、売れた後にトラブルになったりする可能性もありますし、個人間での取引になるため慎重な対策が必要となるでしょう。
⑤人に譲る・ジモティーを利用する
売れるような価値のある釣竿ではないけれど、ただ処分するのはもったいない…と感じる方もいらっしゃいますよね。
そんなときは、友人や親戚など周囲の方に譲るか「ジモティー」のような、地域の情報交換掲示板などで引き取り手を探す方法がおすすめです。
譲渡するだけなら利用手数料も発生しませんし、自宅近隣や最寄り駅での受け渡しなら、もちろん送料もかかりません。
ただし、希望者が見つかるまでは処分できないため、急いで手放したい場合には不向きというデメリットも。
また、ジモティーでは見知らぬ方との個人間取引になるため、確実に受け渡せるようにしっかりと連絡を取り合いましょう。
⑥支援団体へ寄付する
まだ使える釣竿を捨てるのではなく、有効活用してほしい場合は、支援団体を通して国内の施設や発展途上国に寄付するのもいいかもしれません。
お持ちの釣竿を寄付することで社会貢献ができるのはこちらとしても嬉しいですよね。
支援団体に送られた釣竿は、
- 寄付した先でそのまま使用される
- 中古品として販売され、その売り上げが寄付される
といった形で国内の施設や発展途上国に寄付されます。
寄付の方法としては、インターネットで寄付先を検索し、条件を確認した上で行ってください。
なお、支援団体によっては事前に連絡が必要な場合や、直接持ち込みをNGとしているところもあります。
また、基本的に寄付の場合、配送料は寄付する側の負担となります。
弊社が運営する「ユースマイル」にて、寄付・支援活動に取り組んでいます。
釣竿の寄付も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
⑦不用品回収業者へ依頼する
「収集日まで待っていられない…。」
「釣竿以外にも処分したい不用品が山ほどある!」
そんなときは、不用品回収業者へ依頼するのがおすすめです。
不用品回収業者を利用するメリットは以下のとおり。
- 年中無休で対応可能
- 自宅にいながら手早く処分できる
- どんな釣竿でも回収可能
- 釣竿以外の不用品もまとめて回収できる
- 買取サービスや何点かまとめての利用でお得にできる
不用品回収業者はスタッフが運び出し作業をしてくれるため、重いものや自治体では捨てにくいものなどの処分にも大変便利です。
土日や祝日、夜間などの処分も可能ですし、引っ越しに合わせての作業もできるため、処分を急いでいる方にももってこいの方法なのではないでしょうか。
しかし不用品回収業者は、釣竿1本でも回収してもらえますが、人件費や作業費、車両費など諸々の費用がかかるため、不用品が少量だとどうしても割高になりがちです。
そこでおすすめなのが、決められた車両に不用品をいくつ積み込んでも定額になる「積み放題プラン」です。
このプランであれば不用品が増えても決められた料金を上がることがなく、載せられるだけ不用品を処分できます。
さらに業者によっては「買取サービス」も利用できるため、釣竿をはじめとした釣具はもちろん、そのほか買取可能な家具・家電などの不用品があれば作業費から買取額を差し引き、場合によっては無料で利用することも可能なのです。
このように業者ごとにお得なプランがある場合も多いため、見積もりを取って自分に合ったプランを提案してもらいましょう。
悪徳業者に注意!
これだけのメリットのある不用品回収業者ですが、残念ながら中にはいわゆる「悪徳業者」に該当するような業者も存在しています。
悪徳業者にひっかからないためにも、次のような業者には依頼しないようにしましょう。
- 「無料回収」を謳い文句にしている
- 必要な資格の「許可証」を確認できない
- 公式ホームページに具体的な料金や内訳が書かれていない
- 見積もりがわかりにくい
- トラックで街中を走りながら「不用品回収します」と呼び掛けている
なお、不用品を回収するためには次のような資格が必要不可欠です。
| 資格 | 資格の主な内容 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | 一般家庭においてごみの回収や運び出しする際に必要 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 法人からごみの回収や運び出しする際に必要 |
| 古物商許可 | 不用品の買取・売却の際に必要 |
これらどの許可においても、許可証がなく不用品を受け入れることは禁止されています。
悪徳業者の特徴や見分け方、不用品回収業者に必要な「古物商許可」については別ページにて解説しておりますので、詳しくはそちらをご参照ください。
以下のページにて安心して依頼できるおすすめの不用品回収業者についても紹介しております。
業者選びの際にはぜひ参考にしてみてくださいね。
釣竿を処分する際の注意点

釣竿の処分方法について理解したところで、ここで注意したい点についても確認しておきましょう。
売却前に付属品を揃え、メンテナンスする
釣竿を査定に出す前に以下のことをチェックしましょう。
- 標準装備品が揃っているか確認する
- 汚れを拭き取る、釣り糸を取り換えるなどメンテナンスする
- 不要になったら早めに売る
釣竿の購入時に付属していた備品(替えスプール、替え穂先など)は、なるべくすべて揃えてから出すようにします。
釣竿に汚れが付いていた場合は、水洗いや拭き取りなどをしてきれいな状態にしてから出しましょう。
なお、シマノやダイワといった人気メーカーは、年に一回新製品を発売します。
新製品が出るとお持ちの釣竿が「古いモデル」となり、査定額が低くなる可能性があるため、不要になった時点で早めに売却するのがおすすめです。
中には買い取ってもらえない釣竿もある
基本的に釣竿は、どんなものでも一度査定に出すことをおすすめします。
実は、壊れてしまった釣竿であっても、
- パーツの利用が可能
- 修理し再販できる
- 海外での一定の需要がある
などの理由から、折れていても買い取ってもらえることがあるのです。
それと同様に壊れたリールもパーツ利用のために買取可能な場合があるため、まずは問い合わせてみるのがおすすめです。
ただし、どんな釣竿でもいい…というわけではなく、釣具の修理や改造を自分してしまったものに関しては買取不可となることも。
もし買い取ってもらえた場合でも、査定額はかなり低くなってしまうかもしれません。
いつかお持ちの釣竿を売却したいと考えているのであれば、修理・改造しないよう注意しましょう。
分解する場合はケガに要注意
釣竿の多くは、カーボンやグラス、竹などでできており、切断し分解すれば「不燃ごみ」「可燃ごみ」として処分できます。
しかし、いくら細い釣竿と言えども、切断するとなれば工具を使わなければならず、それなりに労力が必要となります。
もしも切断する場合には軍手をし、ケガや事故に注意するとともに、周囲に破片が飛び散っても大丈夫なように配慮した上で行ってください。
釣竿の処分時に出やすい不用品

釣竿を処分する際に、ほかの釣具はもちろん、ライフジャケットやクーラーボックスなどの関連製品もまとめて処分したいとお考えの方も多いかと思います。
ここでは、釣竿を処分する際に出やすい不用品が何ごみにあたるのかを簡単に紹介いたします。
| 品目 | ごみの区分 |
|---|---|
| ルアー・リール・釣り針 | 不燃ごみ・金属ごみ |
| 釣り糸 | 可燃ごみ |
| ライフジャケット | 可燃ごみ・不燃ごみ |
| クーラーボックス | 可燃ごみ・不燃ごみ 大きさによって粗大ごみ |
なお、お住まいの地域によって細かいルールは異なります。必ずホームページや広報、窓口などで確認した上で処分してください。
クーラーボックスの処分方法をはじめ、さまざまなアウトドア・キャンプ用品の処分について詳しく解説した記事もありますので、処分を検討される場合はそちらもあわせてご覧くださいね。
釣竿の処分でよくある質問

Q.壊れた釣竿も回収できるのですか?
A.はい。傷ついていたり、折れていたりする釣竿も回収可能です。ただし、買取はできない恐れがございますのでご了承ください。
Q.絶対に即日対応できるのですか?
A.弊社では可能な限り、ご依頼を受けたら即日対応を心がけております。
それでも混雑状況やご依頼の時間帯によっては、翌日以降のご対応となってしまうこともございます。
もしもご希望の日時があれば、お早めにご予約ください。
Q.見積もりを確認してからキャンセルできますか?
A.はい、もちろん可能です。弊社では、お客様のご承諾なしに作業を始めることはございません。
もしもお見積もり金額にご納得いただけないようでしたらなんなりとお申しつけください。
Q.釣竿の運び出しはやってくれますか?
A.もちろんです。釣竿を含め、不用品の運び出しもすべてサービスに含まれております。
搬出ルートによっては追加料金が発生するものの、その場合は事前に必ずお客様に確認し、ご納得いただいてから作業いたします。
Q.夜間でも回収してくれますか?
A.原則として、弊社の訪問時間は19時までとなっておりますが、お客様のご希望があればできる限り調整いたします。
その際にトラックの手配やスタッフのシフトを調節する必要がありますので、営業時間外での回収をご希望の方はなるべくお早めにご相談ください。
まとめ

今回は「釣竿の処分方法」について解説してきました。
釣竿を普通ごみとして廃棄する際にはパーツごとに分別する必要があるため、少々面倒に感じる方も多いかと思います。
かといって、粗大ごみとして処分するには時間も費用もかかりますし、どうしようとお悩みではありませんか?
「急ぎで釣竿を処分したい!」
「釣竿以外にもまとめて処分したい不用品がある。」
そんなときは不用品回収業者の利用がおすすめです。
弊社「出張回収センター」でも、釣竿を含め、さまざまな不用品を買取・回収しています。
釣竿は古く破損したものでも買い取ってもらえる可能性がありますので、まずは査定に出してみるのがおすすめです。万が一、値が付かなかった釣竿に関しても、そのままお引き取りいたしますので手間は一切かかりません。
見積もり、査定のみであれば無料でご利用いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください!