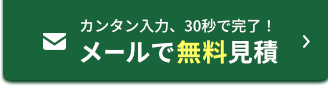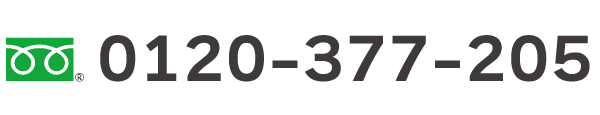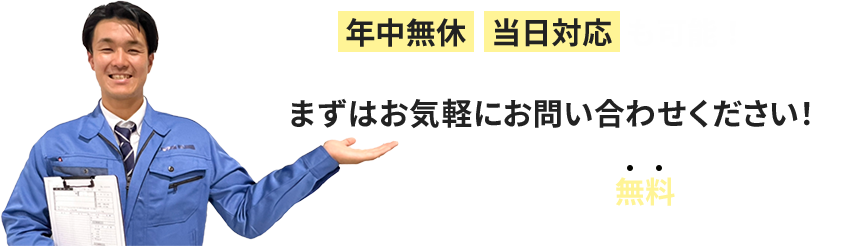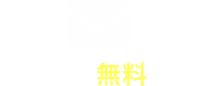家族や大切な人が亡くなった後訪れる「遺品の整理」。
遺品整理とは「故人が生前使っていたものや身の回りのもの、思い出のものを整理すること」を言い、不要なものを処分するといった作業も含まれます。
とは言え、家族を亡くした精神的なショックやほかのさまざまな手続きに追われ、手を付けられずにいるという人も多いもの。
ほかにも「荷物がかなり多い」「遠方で通いにくい」といった事情から、遺品の処分が進まない人もいるでしょう。
今回は遺品の処分方法について解説するとともに、捨てにくい遺品の捨て方などもご紹介します。
なかなか遺品を処分できなかった方も、この記事を参考にスムーズな遺品の処分ができれば幸いです。
■「遺品整理」についてはこちらの記事でも詳しく解説しています■
- 【遺品整理の基本】いつから始める?方法や費用は?疑問点を解説します!
- 【遺品整理のタイミング】大切な人を見送った後、いつから始めるべき?その手順は?
- 「遺品整理」のトラブルで多いものとは?業者・親族間のトラブル事例、巻き込まれないために気をつけたいポイントなど徹底解説!
遺品の処分方法
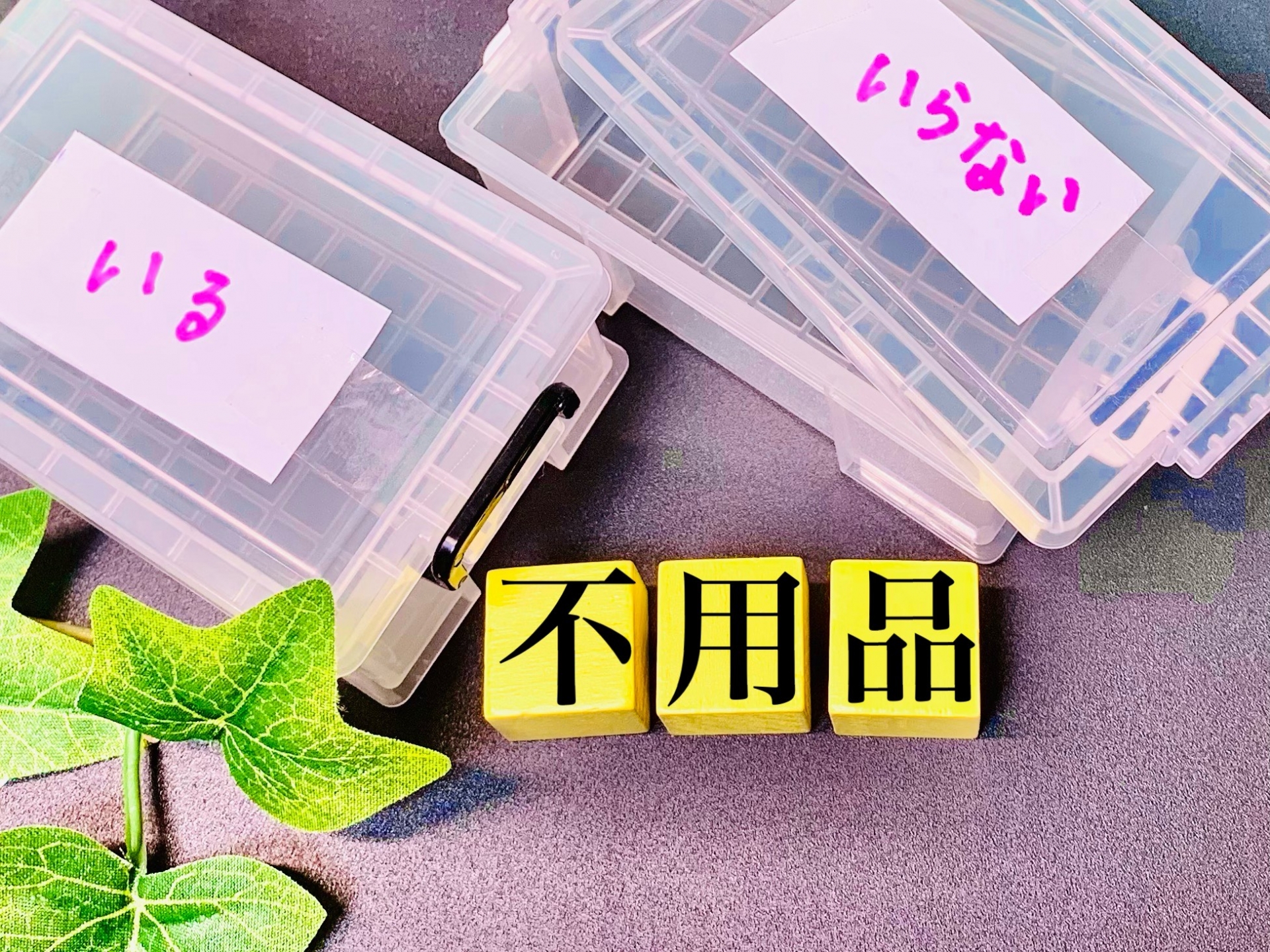
遺品整理で「捨てるもの」「残すもの」の仕分けをおこなったあとは、ごみに出したり売却したり、時には人に譲ったりしながら処分する必要があります。
故人の遺品の量や種類に注意しながら、適切な方法でおこないましょう。
処分方法1.自治体で処分する
自分で遺品整理をおこなった場合、不用品やごみを自治体で捨てるという人も多いでしょう。
自治体では通常、家庭から出る「生ごみ」や「プラスチックごみ」などはもちろん、家電や家具といった粗大ごみも捨てられます。
一般的な家庭ごみである「可燃ごみ」「不燃ごみ」や、「資源ごみ」などを捨てる場合は無料ですので、指定ごみ袋を用意するだけで済むでしょう。
ただし、自治体のルールに従ってごみを分別する必要があるうえ、地域によっては一度に大量のごみを捨てられない場合もあります。
また自治体では捨てられない「リサイクル家電」(エアコン・テレビ・洗濯機・冷蔵庫)の扱いに注意してください。
多くの自治体では30㎝角以上や50㎝角以上のものなど、ごみ袋に入らない大きさのものは粗大ごみ扱いです。
粗大ごみに関しては「事前の申し込み」が必要となり、手数料も発生するため気を付けましょう。
一般的な粗大ごみの利用手順は以下のとおりです。
- 粗大ごみ受付センターへ電話かネットで予約を入れる
- 粗大ごみの手数料を確認する
- 手数料納付券シールを販売店(スーパーやコンビニなど)で購入
- 手数料納付券に必要事項を記入し、ごみに貼る
- 当日の朝8時までに指定場所へ運び出しておく
「粗大ごみ」で捨てる場合、通常の「可燃ごみ」や「資源ごみ」などと違って回収日が少ないという点も注意しなければなりません。
多くの自治体で粗大ごみは月に1回程度の回収となっており、申し込みから回収日までは数日かかるのが一般的です。
タイミングによっては1か月程待たなくてはならず、なかなか家の中が片付かないこともあると知っておきましょう。
また、「不燃ごみ」に関しても地域によっては回収日が少なく、例えば愛知県名古屋市では「月に1回」と粗大ごみと同じ扱いです。
遺品整理で出るごみの量は時に大量となる場合がありますので、回収日がいつなのかチェックしてからおこなうのがおすすめです。
処分方法2.自治体のごみ処理施設へ持ち込む
各自治体にあるごみ処理施設へ、自分でごみを持ち込むという方法もあります。
自治体の戸別回収は一度に回収できるごみの量が2~3袋までと限られている場合があり、その時は何回かに分けて出さなければなりません。
さらに回収日が決まっているため、その日に出せないときは次の回収日まで待つ必要があります。
一方、自分で持ち込む場合は、ごみ処理施設の営業時間内であればいつでも利用できるというメリットがあります。
さらにごみの量も制限がないため、大量のごみであっても「1日で処分する」ということも可能です。
このように便利な方法ではあるものの、自分での持ち込みは「車のみ」の利用がほとんど。
運転ができない方や車両を持っていないという方は運転者を探したり、レンタカーを借りたりと手段を見つける必要があります。
また、処理施設によるものの、車両への積み降ろしは各自でおこなうのが一般的で、捨てたいごみの大きさや量によっては一人でおこなうのが困難でしょう。
ごみ処理施設への持ち込み手順は自治体によって異なりますが、ここでは愛知県名古屋市を例に手順をご紹介します。
- 「可燃ごみ」と「不燃・粗大ごみ」に分別
- ごみを車両に積んだ状態でお住まいの区の環境事業所へ行く
- 環境事業所で受付後、指定のごみ処理施設へごみを持ち込む
- ごみ処理施設にてごみを計測後、10kgまで200円を現金で支払う
申し込みについては「事前予約制」や「当日受付制」など自治体や施設によって異なります。
例えば名古屋市では「当日受付」となりますが、受付場所は環境事業所となり、ごみ処理施設での受付はできません。
また、大阪市の場合は「前日までに処理施設へ電話予約が必要」となっているなど、自治体ごとに手順が異なるため注意しましょう。
処分方法3.業者に依頼する
ここまで自分たちで遺品を捨てる方法をお伝えしてきましたが、遺品の処分というのは思った以上に大変であることも多いものです。
「捨てる遺品の量が多い」「故人の家に通うのが大変」「片付けに時間が割けない」といった物理的な問題はもちろんですが、「遺品を見るのが辛い」「悲しみから立ち直れていない」といった精神的な苦痛も遺品の処分の妨げになりやすいです。
こうした事でなかなか作業が進まない、という場合は「業者へ依頼する」のがおすすめです。
業者には以下のようなものがあります。
- 遺品整理業者
- 不用品回収業者
- 便利屋
「遺品整理」と名が付くように、遺品整理業者であれば遺品の仕分けから処分、遺品の供養や手続きの代行なども任せることができます。
多くの遺品整理業者では「遺品整理士」が在籍しており、遺品に対して専門知識を持ちきめ細やかな対応が期待できるでしょう。
単に遺品整理をおこなうだけでなく、遺族の気持ちに寄り添いながら家の片付けを進めてくれるのが遺品整理業者の強みです。
一方、「不用品回収業者」や「便利屋」などにも業者によって遺品整理士が在籍しているところもあり、そのような業者では遺品整理についても丁寧に対応してもらえます。
このような業者は「不用品の処分」や「家の修復」「室内の掃除・片付け」に力を入れていることが多いため、状況に合わせて利用してみてはいかがでしょうか。
また、遺品の仕分けまでは自分でおこない、捨てにくいものの処分だけを依頼することで費用も抑えることができるでしょう。
このような業者は自宅までスタッフに来てもらえるので、ごみの運搬や家具の解体などをすべて任せることができます。
業者によっては、故人の体液や害虫の処理、消臭作業といった「特殊清掃」にも対応している業者がいるなど得意分野はさまざま。
ハウスクリーニングにも対応している業者であれば、部屋の掃除もおこなってくれるため、賃貸で退去の必要がある場合や家の売却を考えている方にも便利です。
■遺品整理業者についての記事はこちらがおすすめです■
処分方法4.売却する
遺品を「捨てる」のではなく「売却」して手放す方法もあります。
売却することができれば、遺品整理の際の処分費用を軽減することもできるでしょう。
ちなみに遺品の売却の場合、「譲渡所得の特別控除」という控除があり、50万円以下は非課税となります。
売却方法は次のような方法があります。
- 買取店に依頼する
- 不用品回収業者・遺品整理業者へ依頼する
- フリマサイト・ネットオークションに出品する
買取店とは専門の分野に特化した買取専門店やリサイクルショップのこと。
お手持ちの遺品を高く買い取ってほしいとお考えの場合は、このような買取店へ出すのがおすすめです。
特に貴金属や着物、骨董品や美術品、フィギュアなどは人によって価値が大きく変わるため、専門店へ査定に出す方が高く買い取ってもらいやすいでしょう。
一方で不用品回収業者や遺品整理業者でも買取に力を入れている業者もおり、「不用品の処分」や「家の片付け」と同時に依頼できるのがメリットです。
手間をかけず、短時間で買取もしてほしい場合はこちらの方が便利でしょう。
ただしこのような業者では買取のみはおこなっておらず、「回収・処分・仕分け・清掃費用など」から「買取費用」を差し引いて利用することになります。
買取対応できるかや買取品目については業者によって異なるため、見積もり時に確認しておくのがおすすめです。
また、時間に余裕がある方は「フリマサイト・ネットオークション」などを利用する方法もあります。
自身で価格を決められるため買取店よりも高く売れる可能性はありますが、必ず売れる保証はありません。
遺品整理においては処分を急ぐ場合もあるため、時間や手間をかけられる方に限った方法となります。
処分方法5.寄付をする
「売却はできなかったけど、捨てるのはもったいない」というような、まだ使えるものであれば寄付をするという選択もあります。
寄付できるものの品目や条件などは支援団体や施設などによって異なるため、まずは寄付先があるかどうかを検索してみましょう。
当社REPROZホールディングスでも寄付活動をおこなっており、「ユースマイル」で寄付を受け付けています。
手順は不用品を段ボール箱に詰めて送るだけですので、気になる方は該当する品目があるかチェックしてみてください。
ただし、こうした寄付活動は、寄付する側が配送料を負担することがほとんどです。
また、いきなり送るのではなく事前に支援先へ連絡しなければならない場合もあるため、利用方法を確認してからおこなうようにしましょう。
処分方法6.親しい人に形見分けをする
故人が大切にしていたものは、親しい人に譲る、つまり「形見分け」をするという方法もあります。
亡くなった人が大切に使っていたものを譲りうけることで供養になり、思い出を振り返るきっかけにもなるでしょう。
形見分けをおこなう時期に決まりはありませんが、多くの場合は四十九日の法要のときと言われています。
形見分けをおこなう品は「アクセサリー」や「眼鏡」「着物」といった身に着けていたものや「文房具」や「杖」などの日用品、「釣り道具」「ゴルフクラブ」といった趣味のものなどさまざまです。
ただし形見分けをおこなう際は、もらう側の気持ちも考え負担にならないようにすることが大切です。
例えば維持に費用がかかる時計や、贈与税がかかるような高価なものなどは気を付けなければなりません。
■形見分けについて詳しい記事はこちらがおすすめです■
遺品の処分方法を選ぶポイント

遺品の処分方法にはいくつかありますが、どの方法で処分すればいいのか迷われることもあるかもしれません。
そうした場合は、以下の条件に当てはまるかどうかを確認してみると選びやすくなります。
時間があるかどうか
現代の日本は核家族化や大都市圏への人口集中のこともあり、ご遺族がそれぞれ遠方に住んでいて、遺品整理の時間どころか、葬儀でご遺族全員が集まれるタイミングを作ることすら難しいことも少なくないでしょう。
また、故人が集合住宅にお住まいになっていた場合だと、当月末もしくは翌月末に解約する必要がでてきますので、それまでに遺品整理や家の片付けを済ませなければならないケースもよくあります。
そんなときは、葬儀社に葬儀だけでなく遺品整理も依頼する方法があります。
特にお仕事をされている方が葬儀や遺品整理を取り仕切ることになった場合、同じ葬儀社に遺品整理もまとめて依頼することで打ち合わせにかかる時間を短縮できます。
場合によっては葬儀と遺品整理を一緒に契約することで割引を受けられるケースもあるのでお得に遺品整理できる場合も。
特殊清掃や掃除が必要かどうか
故人がお亡くなりになってから時間が経過していたり、家が片付けられていなくてゴミ屋敷状態になっていたりする場合は、清掃・特殊清掃を取り扱っている不用品回収業者をおすすめします。
この場合、ご遺族だけでは原状回復が難しい可能性が高いです。
特に、特殊清掃が必要な場合だと臭いが強烈で部屋に入ることすら難しかったり、掃除をしても市販の掃除用品では臭いや汚れが取れなかったりすることがあります。
そのため、掃除のプロに仕事を任せて家を元のきれいな状態に戻しましょう。
予算に余裕があるか
予算に余裕が無く、とにかく安く遺品を処分されたいという場合は、不用品回収業者がおすすめです。
不用品回収業者ではトラック積み放題プランが用意されており、業者のスタッフが家の中にある大量の不用品をトラックに積めるだけ積んで処分いたします。
また、多くの不用品回収業者は古物商許可を取得していて、電化製品や家具の買い取りにも対応しています。
そのため、買い取りを利用することでさらに処分費用を安く抑えることが可能です。
遺品整理を取り扱っている不用品回収業者も年々増えておりますが、万が一遺品の取り扱いに関して心配な部分があるのであれば、遺品整理士資格を取得したスタッフがいる不用品回収業者のご利用をおすすめします。
思い入れのあるものがどれくらいあるか
遺品整理や不用品回収で外部の者に遺品の処分を依頼した場合、回収するかどうかを一つ一つ確認しながら作業を進めるのが基本です。
しかし、ご遺族の思い入れのあるものがたくさんある場合、間違って思い入れのあるものとわからずに処分してしまう可能性も。
そのため、生まれ育った実家を処分する場合など、思い入れのある物がたくさんある場合や、大切なものに触れてほしくない場合は、時間がかかってもご遺族の皆様で作業をされた方が無難でしょう。
時間があまり無い場合は、ご遺族だけで形見分けするものをある程度避けておいてから、不用品回収業者に任せるのもおすすめです。
遺品整理で捨てにくいものはどうする?

遺品の処分を進めているとよくある問題が「遺品を捨てられない」ということ。
思い出が詰まった遺品を捨てるかどうかの判断は、遺族にとって負担のかかる作業です。
ここでは捨てにくいものをどのように対処するか、処分の方法やポイントをお伝えしていきます。
遺品が捨てられない理由
大量のごみや大きな家具・家電ではなくても、なかなか処分に踏み切れないという遺品もあります。
よくある「捨てにくいもの」は次のようなものです。
- 思い出が詰まったもの(故人が大切にしていたもの・よく身に着けていたものなど)
- 写真・アルバム・手紙など
- 仏壇・位牌・神棚など捨て方がよくわからないもの
- 人形、置物など捨てるのに心理的抵抗があるもの
- 価値がわかりにくいもの(宝石や美術品など)
これらは仕分けの段階ですぐに捨てられるというものではなく、いつまでも残っていたり処分できなかったりするものです。
不要なものは思い切って処分し、心の整理を進めてみましょう。
処分のポイント1.思い出の品、写真などはデータにしてみる
遺品整理を進めているとどれも「思い出の品」であることから、残すものが増えてしまうということがあります。
いつも身に着けていたものや趣味のもの、大切にしていたものは処分するのが気が引けるということも多いですよね。
しかし、すべてを残す必要はありません。
これらは写真に撮ってデータ化することで保管スペースを減らすことができます。
本当に手元に置いておきたい、残したいものだけを保管し、残りはデータで保存してみてはいかがでしょうか。
見返したいときはいつでも見れるので、「思い出の保管」もできる良い方法です。
同じように写真やアルバムもデータ化できるものはおこない、物理的なスペースを減らすとよいでしょう。
処分のポイント2.仏壇や位牌、人形などは供養を依頼する
実家の整理をしていると「仏壇」や「位牌」といった宗教的なものがあることも多いものです。
近年では住宅事情から置いていない家庭も増えましたが、古い家や地方ではどの家庭でも置いてあるのが一般的でした。
遺品整理でこれらを処分する場合、正しい手順や費用を心配される方も多くいます。
この場合、お寺や神社に持ち込んで供養やお焚き上げをしてもらうのが一般的な手順です。
普段お世話になっている檀家があればそちらに問い合わせることでスムーズに処分できるでしょう。
仏壇や位牌の場合、魂入れなどの開眼供養をおこなっている場合は魂を抜く作業「閉眼供養」もお願いします。
このような供養やお焚き上げは宗教的なものだけでなく、人形やぬいぐるみなどにも有効です。
捨てるのは気が引ける…というものがあれば、一緒にお願いするとよいでしょう。
最近では神社やお寺に郵送で依頼できることや、遺品整理業者、不用品回収業者でも依頼できる場合があります。
業者であれば大きな仏壇もそのまま引き取ってもらえるため、状況に合わせて利用してみてください。
処分のポイント3.宝石や美術品、骨董品は専門家へ査定を依頼
宝石や美術品など、遺族では価値が分からないものも出てくることがあります。
このようなものは安易に処分せず、専門家へ査定を依頼してから対応を考えましょう。
もし価値が高いものであれば相続財産の対象となることもあります。
家族間であっても知らずに分けてしまうと後にトラブルとなる可能性もあるため、話し合いをおこなうことが大切です。
遺品の処分で気を付けたい注意点

ここでは遺品の処分について注意点をご紹介します。
個人で勝手に作業しない
一般的に遺品整理は「相続人」がおこなうため、残された子どもや配偶者、きょうだいなどで作業を進めます。
とは言え、一度に相続人が集まれる機会が取れないという人もいて、遺品整理がスムーズに進まないケースもあるかもしれません。
そんな時であっても、個人で遺品の処分を進めることがないよう注意してください。
個人で勝手に作業を進めると、捨ててはいけないものを処分したり、ものを紛失したりしてトラブルに発展する可能性もあります。
個人で作業する場合はあらかじめ家族間で相談をし、確認しながら作業を進めましょう。
自治体でごみを捨てる場合は正しい分別を
遺品の処分を自分たちでおこなう場合、自治体で不用品を処分することも多くあるでしょう。
しかし、遺品整理の場合は普段住んでいない地域での作業ということもあるかもしれません。
遺品の処分の際は、分別方法に気を付けておこなうようにしましょう。
特に注意したいのが、自治体では捨てられないごみの処分についてです。
以下のものは自治体では捨てられない、または捨てられない可能性が高いため注意してください。
| 対象品目 | 自治体での取り扱い・処分方法 |
|---|---|
| リサイクル家電(エアコン・テレビ・洗濯機(衣類乾燥機)・冷蔵庫(冷凍庫)) | ・自治体では回収不可 ・家電リサイクル法に従って処分 |
| パソコン | ・一部の自治体では小型家電リサイクル法に基づいて回収 ・メーカーや販売店で回収してもらう |
| 危険物・処理困難物(ピアノ・灯油・ガソリン・金庫・バッテリー・コンクリート・土、石・消火器など) | ・基本的に自治体での回収は不可 ・自治体や販売店、メーカーに問い合わせる |
| 事業系ごみ | ・店舗やオフィスなど、事業活動で使われたごみは家庭ごみでの回収が不可 ・一般廃棄物処理業者または産業廃棄物処理業者に処分を依頼する |
実家の片付けをしていたら金庫や灯油といった自治体では捨てられないものが出てきた、ということもあるかもしれません。
遺品の処分をおこなう自治体での、ごみルールについて確認しながら作業を進めましょう。
遺品整理でよくある質問
Q.当日立ち会いができないのですが依頼は可能ですか?
A.お客様が遠方にお住まいなどの理由で立ち会いできない場合の遺品の処分も対応しております。
実際に立ち会い無しでのご依頼も多く引き受けております。
この場合は事前にお客様と電話やメール、LINEで打ち合わせを行ったうえで作業に取り掛かります。
万が一処分すべきかわからないものがございましたら、保留ボックスに入れてお客様のご自宅にお送りしてお客様ご自身に処分するか判断していただいております。
万が一お客様からのご希望があれば、作業中の映像配信や作業後の画像の送付にも対応しておりますのでお気軽にお申し付けください。
Q.大きな遺品を自宅に送ってもらうことは可能ですか?
A.もちろん可能でございます。
たんすなど大きくて運ぶのが難しいものを処分せずに保管する場合、大切な遺品に傷がつかないように梱包したうえでお客様のご自宅にお送りいたします。
Q.時間が経過して臭いが取れなかった部屋の清掃や遺品の処分も任せられますか?
A.当社は特殊清掃にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
実際に当社では他社に依頼しても臭いが取れなかったケースも多数引き受けております。
臭気測定器を用いて徹底的に臭いの原因を突き止め、原状回復いたします。
Q.遺品でも買取はしてもらえるのでしょうか?
A.はい、もちろん遺品であっても買取は可能でございます。
遺品整理の際に、不要なもので売ってしまいたいものがございましたら、お気軽にお申し付けください。
Q.遺品整理の後に掃除はしてもらえますか?
A.はい、遺品整理後の清掃も承っております。
当社は、遺品整理だけでなくハウスクリーニングもおこなっておりますので、安心して当社スタッフにお任せください。
Q.遺品の供養はしてもらえますか?
A.はい、ご希望であれば遺品の供養も行なっております。
当社は大須の寺院と提携しているため、精抜きや遺品の合同供養サービスもご利用いただけます。
必要に応じては僧侶をご自宅まで呼ぶことも可能ですので、ご希望でしたらお問い合わせの際にお気軽にご相談ください。
まとめ

今回は遺品の処分方法についてお伝えしてきました。
遺品の中には「捨てにくいもの」や「処分すると気が引けるもの」も出てくるかもしれません。
すべて残したいと考える方もいるかもしれませんが、保管スペースの問題や自分の子ども、さらに孫たちに整理の問題を残してしまうということも懸念されます。
なるべく不要なものは処分をし、残された遺族が前向きに生活できるきっかけになれば幸いです。
遺品の処分について、負担が大きいと感じる場合は業者の利用を検討してみましょう。
特に大きな不用品やごみが大量に出てしまう場合には、自分たちでおこなうのが難しいことがあります。
業者の手を借りることで気持ちが落ち着き、スムーズに遺品整理ができることもありますので、相談してみてはいかがでしょうか。
当社「出張回収センター」でも遺品整理をおこなっており、遺品整理士も在籍しています。
不用品の処分・買取はもちろん、家の清掃、空き家の解体などオプションサービスも充実していますので、ぜひ一度ご相談ください。