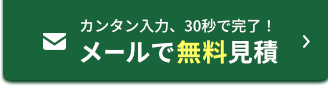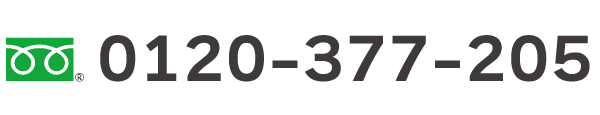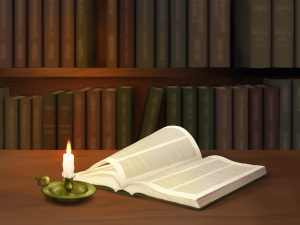日本特有の「間仕切り建具」として和室には欠かせない襖(ふすま)や障子ですが、洋室が主流となった現代では、襖・障子が使われる数も減少しています。
古い団地や日本家屋などにはまだ和室がある家も多いですが、押し入れの襖を取りはらってワークスペースにしたり、襖や障子を撤去し和室をつなげて一部屋にしたりと、あえて襖を使わないという方も多くいらっしゃるようです。
今回のコラムでは、不要になった際、捨てるのが難しい襖・障子のさまざまな処分方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
【この記事でわかること】
- 襖や障子の捨て方
- 襖と障子の違い
- 簡単に襖・障子の処分をおこなう方法
襖・障子の処分方法

襖や障子を捨てる際は「粗大ごみ」として捨てるのが一般的ですが、地域によって「建具扱い」となるため、ごみとして処分できないことも。
粗大ごみとして襖や障子を処分する方法、粗大ごみとして処分できない場合の処分方法などを、それぞれ詳しくお伝えしていきます。
処分方法1.自治体の粗大ごみで処分
襖や障子は、「粗大ごみ」で処分できる自治体がほとんどです。
ただし自治体によっては「建具」に分類され、その場合は「処理困難物」となります。
処理困難物となった場合は、自治体での粗大ごみ回収は利用できないため注意が必要です。
お住まいの自治体で襖や障子を粗大ごみで収集可能か調べるには、各自治体のホームページの品目一覧などを参考にしてみてください。
今回は名古屋市を例に、粗大ごみの収集方法をご説明します。
- 電話またはインターネットで粗大ごみ受付センターへ連絡し、予約をする
- コンビニやスーパーなどで粗大ごみシールを購入する
- 予約番号をシールに記載し、見える場所に貼り付ける
- 指定日の当日の朝に指定の場所に運び出す
名古屋市の場合、襖は粗大ごみとして回収してもらえます。(手数料は250円)
一方、障子は品目一覧に記載がないため、確認が必要です。(2025年1月時点)
自治体での粗大ごみ回収は、処分費用が数百円程度と安く処分できる一方、「家からの運び出しは自分でおこわなければならない」「回収日が少ないため、すぐに捨てられない」といったデメリットも。
すぐに捨てたいという場合は、ごみ処理施設への持ち込みが便利です。
処分方法2.自治体のごみ処理施設へ持ち込む
襖や障子の運搬手段がある方は、直接ごみ処理施設へ搬入することも可能です。
多くの自治体ではごみ処理施設への持ち込みを受け付けており、営業時間内であればいつでもごみを捨てることができます。
粗大ごみの戸別回収とは違い、事前予約が不要な場合もあるため、都合の良い日にすぐに捨てられるのがメリット。
ただし、車での持ち込みが一般的ですので、車や免許がないと難しいでしょう。
特に襖や障子を運搬するとなると、大きな車両が必要になります。
また、持ち運びや車両への積み込みも自分でおこなう必要があるうえ、処理施設までの場所が遠ければ時間も要します。
あらかじめ手順や処理施設の場所を確認してからおこないましょう。
例として、名古屋市での自己搬入の手順をご紹介します。
- 搬入するごみを車両に積んだ状態で、受付時間内に区の環境事業所へ行く(区によって受付時間が異なるので注意)
- ごみをチェックしてもらい、受付をおこなう
- ごみ処理施設へごみを搬入(粗大ごみは港区の大江破砕工場のみ)
- 処理施設で計量をおこない、重さごとの処理手数料を支払う
多くの自治体では直接搬入の場合、処分手数料は重さで計算します。
名古屋市では10㎏ごとに200円、大阪市では10㎏ごとに90円と地域によって異なるため、ご確認ください。
処分方法3.解体してごみに出す
襖や障子は、解体して一般ごみと一緒に処分するという方法もあります。
この方法であれば、粗大ごみとしての回収をおこなっていない地域でも普通ごみとして出せるため「無料」で捨てられます。
もともとDIYが趣味、という方なら工具を用意する必要もなく、費用がかからないのが大きなメリットといえるでしょう。
ただし、量産襖のような簡素な造りのものであれば比較的簡単に解体できますが、本襖のように何度も和紙や布を重ねてあるものや、釘を使用しているものは解体するのが難しくなります。
作業するスペースを確保でき、時間と手間がかかってもいい、ということでしたら一度チャレンジしてみてもいいかもしれません。
襖・障子を解体するのに便利な道具と注意点
襖・障子を解体する際にあると便利な道具は以下のとおりです。
- ノコギリ
- 釘抜き
- 厚手の軍手
- ダンボール
- ビニールシート
ダンボールやビニールシートは解体の際に、襖や障子の下に敷いて使用します。
そのほか、軍手やビニールひもなどは100均でも揃えられますが、ノコギリや釘抜きなどはホームセンターでしっかりした造りのものを購入した場合、数千円程度出費が必要になることもあります。
必要な道具を揃えずに無理やり解体した場合、ケガの恐れや周りの壁や床を傷つけてしまうなど、思わぬトラブルを引き起こす可能性も考えられるため、しっかりと準備をしてから作業を始めてください。
また、解体の際に騒音が発生してご近所トラブルになることもあるので、作業する時間帯や、作業時に出る騒音に配慮しつつ作業をおこなうようにしましょう。
解体後の捨て方は?
小さく解体した襖・障子は一般ごみとして出すことが可能です。
釘や金属製の取っ手は分別して「不燃ごみ」に、ふすま紙、障子紙や中の木材は「可燃ごみ」として出しましょう。
処分方法4.フリマアプリ・ネットオークションに出す
襖や障子は、フリマアプリやネットオークションを利用して売却するという方法もあります。
汚れや傷みのある襖・障子は出品しても売れないことが多いですが、新品に近いものや、アンティークの襖・障子であれば売却できることもあります。
また、襖本体は売却できなくても、襖から取り外した引き手などのパーツが売却できることも。
「建具」で検索すると出品例が見られるため、一度チェックしてみるのもよいでしょう。
ただし、売却できた場合は手数料がかかる点と、襖・障子はサイズが大きく送料が高額になる点に注意が必要です。
出品額を決める際は手数料・送料がどのくらいかかるか調べ、損にならない金額で出品するようにしましょう。
また、出品したとしても売れる保証はありません。
売れなければ不要な襖・障子を持ち続けていなければならないというデメリットもあり、急ぎの場合には向いていない手段となっています。
処分方法5.ジモティーを利用
まだキレイな襖や障子をお持ちでしたら、人に譲って使ってもらうという方法もあります。
身近に譲る友人がいない場合は、「ジモティー」を利用して譲り先を探してみてはいかがでしょうか。
ジモティーとは、不用品を譲ることのできるネット上での掲示板で、フリマサイトとは違い「無償」で譲ることもできます。
直接手渡しする方法を選べば配送料や梱包が必要ないため、手軽に手放せる方法です。
ただし、人に襖や障子を譲る場合は、必ずサイズを確認してもらいましょう。
できれば写真などで確認してもらうのではなく、譲る前に一度、実際の襖・障子の状態・サイズをあわせて確認してもらうのがベストです。
また、この方法もすぐに譲り手が現れるとは限りません。
フリマアプリ・ネットオークションと同じく、急ぎで処分したい場合には向いていない方法となっています。
処分方法6.不用品回収業者に依頼
これまでいくつか襖・障子の処分方法についてお伝えしてきましたが、次のようなお悩みがありましたら不用品回収業者への依頼がおすすめです。
- 自治体の粗大ごみでは襖や障子を回収してもらえない
- 処分する襖や障子が多く、ごみに出すのが大変
- 襖や障子の他にも実家のお片付けで出た不用品がたくさんある
- 引っ越し前に急いで不用品を片づけてしまいたい
自治体で襖や障子を粗大ごみに出せた場合、もしくは解体して一般ごみと一緒に処分できた場合は、費用は安く済むものの、手間や時間がかかってしまいます。
襖や障子のように大きなサイズのものは、なるべく簡単に捨てたいですよね。
不用品回収業者では、大きな家具や電化製品を含め、基本的にはどんなものでも回収してくれます。
スタッフが自宅まで来てくれるため、運搬や分別の手間がかかりません。
重たい本襖や障子が複数枚ある場合や、解体を途中であきらめてしまった襖や障子なども、素早く処分してもらえます。
もちろん襖や障子1枚からでも回収は可能ですが、他にも不用品があるなら一緒に回収を依頼すると1点にかかる費用を抑えることができます。
買取もおこなっている業者を選べば「ごみ」だと思っていた不用品に値が付くこともあるため、お得に襖や障子の処分ができますよ。
不用品回収業者について、以下の記事で詳しく紹介していますので参考にしてみてください。
襖・障子の違いとは?

そもそも自分の家の間仕切りが襖なのか障子なのか、はっきりとその区別を説明できる方は少ないのではないでしょうか?処分において「襖・障子」は同じ扱いにされることがほとんどですが、その違いは以下のようになっています。
襖(ふすま)とは
「襖(ふすま)」とは、木材などで作られた格子状の組子に和紙や布を何度も貼って仕上げ、引手(襖の開閉の際に手をかける部分)をつけて間仕切りにしたもの。
何度も和紙や布を重ねて貼っていることから保温性に優れており、透けないことから押し入れの引き戸や部屋の仕切りとして利用されています。
襖には、「本襖」「戸襖」「量産襖」といった種類がありますので、順番にみていきましょう。
本襖(和襖)
本襖(和襖)は、補修紙、茶チリ紙、ふすま紙など、何種類もの紙を貼り重ねて作られる襖です。
何度も張り替えることが可能で、枠が歪みにくく耐久性があるのが特徴。
ただし購入時の価格は高価なものが多くなります。
補修の際は枠や引手を外し、和紙をそのまま貼り重ねていくことがほとんどですが、剥がして補修することもできます。
戸襖(とぶすま)
戸襖(とぶすま)は、組子にベニヤ板を貼ったものを下地にしてできている引き戸で、洋室と和室を仕切るために使用されることが多いもの。
洋室と和室それぞれの雰囲気に合わせ、和室側は襖紙、洋室側は木材や壁紙などが貼られて作られており、現代の住居でも使用されます。
木材を使用していることから頑丈な造りをしていますが、襖部分(和紙を貼った部分)が傷んだ場合は貼り重ねていくしかなく、また素材が異なるものを両面に貼り合わせていることから、反りやすいという欠点があります。
量産襖
量産襖は、発泡スチロールやプラスチック、段ボールなどを下地にして作られた襖です。
簡易な造りをしているため量産可能で扱いやすく、安価で手に入るのが特徴ですが、耐久性が低いため、何度も和紙を張り替えられないというデメリットもあります。
補修する場合、枠は外さずそのまま貼り重ねていきます。
障子とは
「障子」とは、木材などで作られた格子の片方の面に、薄い和紙や障子紙を貼ったもの。
襖と同様、基本的には部屋の間仕切りをするのに使われます。
襖との大きな違いは「採光ができる」という点。
薄い障子紙を1枚しか貼らないことによって、外部からの視線を遮りつつ部屋の外の光を取り入れられます。
ただし、薄い和紙や障子紙を使用することから開閉時に破れやすいのが難点。
そのため、障子紙は貼り替えを前提とし、水洗いでキレイに落とせる糊を用いて貼ります。
障子は格子が模様になっているものや、模様が印刷された障子紙が販売されており、襖とは違った楽しみ方ができます。
襖・障子の処分時に出やすい不用品

ここでは襖や障子の処分時に出やすいものや、類似品の処分方法についてご紹介します。
それぞれの記事内に処分方法が記載されていますので、参考にしてみてください。
- 網戸の処分方法6選!寿命の見極め方は?便利な処分方法も解説
- すだれの捨て方7選!売却はできる?処分費用・注意点なども紹介
- カーテンの処分方法7選!無料回収はある?費用や注意点も解説
- ブラインドの処分方法7選!中古でも売れる?費用や注意点も解説
- カーテンレールの処分方法!引き取りは可能?取り外しの手順も解説
襖・障子の処分でよくある質問

当社「出張回収センター」では、襖や障子の回収もおこなっています。
ここでは、利用の際にお客様からよくある質問についてまとめましたので、参考にしてみてください。
Q. 回収してもらう前に襖や障子を外しておく必要はありますか?
A. 回収に伴う作業はすべて当社のスタッフにお任せください。損傷や騒音に配慮しながら丁寧に作業いたします。
Q. 今日中に回収してもらうことはできますか?
A. はい、当社ではご連絡いただいた当日の回収にも対応しております。先にご予約いただいているお客様との兼ね合いはございますが、名古屋近郊であれば最短30分で伺うことが可能です。まずは、お早めに電話でお問い合わせください。
Q. 襖や障子と一緒に畳や婚礼タンスも回収してもらえますか?
A. もちろん、大丈夫です。出張回収センターでは畳や婚礼タンスも回収可能です。大きなものや重たいものでもお任せください。
Q. 仕事が忙しいので土日に来てもらうことはできますか?
A. はい、当社は年中無休で土日祝日にも営業しております。ご希望の日程に合わせて伺いますので、お気軽にご相談ください。
まとめ

襖や障子の処分方法について解説してきました。
処分の際には「住んでいる自治体で捨てられるか?」や「襖・障子の運搬を自分でできるか?」がポイントになります。
襖や障子の処分は、自治体では安く捨てられますが、運搬がネックという方も多いでしょう。
「一人暮らしで襖や障子などを持ち運ぶのが難しい」「遠方の実家を片付けたい」という方は、不用品回収業者を利用するのも一つの手段です。
「出張回収センター」でも襖や障子をはじめとした不用品の回収・買取をおこなっています。
タイミングによっては即日対応ができ、土日や祝日、夜間など都合に合わせた作業も可能です。
LINEやメールでの見積もり・相談もできますので、お気軽にご相談ください。